令和の米騒動って、なにが起きてるの?
最近よく聞く「米が足りない」「米が高い」という声。2025年の春、日本では再び「米騒動」と呼ばれるほどの混乱が起きています。
でも一体なにが原因で?どうしてここまで深刻になったの?あっさり疑問を投げるメカミンに対して、あしもんが全力で解説してくれました。
1. 米が足りないってどういうこと?
米って、ほんとに足りないの?
足りないよ。しかも「少し足りない」レベルじゃなくて、構造的にかなり深刻。
2023年と2024年に連続して起きた猛暑と高温障害のせいで、全国的にお米の収穫量が大きく減ったんだ。
たとえば2023年、新潟県産コシヒカリの「一等米」比率は、例年80%超だったのに、なんと4.9%まで激減。
そしてこの影響は翌年にも残る。政府備蓄米を放出しても追いつかず、2025年には市場の供給がさらに逼迫してしまった。 さらに追い打ち:
2023年と2024年に連続して起きた猛暑と高温障害のせいで、全国的にお米の収穫量が大きく減ったんだ。
たとえば2023年、新潟県産コシヒカリの「一等米」比率は、例年80%超だったのに、なんと4.9%まで激減。
そしてこの影響は翌年にも残る。政府備蓄米を放出しても追いつかず、2025年には市場の供給がさらに逼迫してしまった。 さらに追い打ち:
- 観光客が激増して、外食業界で米の消費が急増
- 家庭でも物価高の中、パンより米を選ぶ人が増えた
- なのに農水省の予測が甘く、生産抑制が続いていた
2. 異常気象でお米がピンチ!?暑さが与える深刻な影響
暑すぎたって、そんなにやばかったの?
めちゃくちゃヤバかった。登熟に必要な温度を大きく超えて連日35℃超え。
その結果:
その結果:
- 白未熟粒(白く濁って商品にならない)
- 胴割れ粒(精米で割れる)
- 収量の減少(実が入らない)
今後もこんな暑さが続くの?
続く可能性は高い。気温は今後さらに上がる予測で、2100年には+4℃以上とも。
農業の対策:
農業の対策:
- 高温耐性品種への切替(例:にじのきらめき)
- 田植え時期を調整して暑さ回避
- 水多めで冷却
3. 農家に「作るな」って言ってたの?それほんと?
農家って、米作るなって言われてたの?
実質的にはそうだよ。農水省は「主食用米は前年並みに抑制」として、毎年目安を出していたんだ。
そもそも「減反政策」ってなに?
減反(げんたん)政策は1970年代から続いた制度で、米が余りすぎて価格が暴落した時代に、農家に「米を作らず他の作物を作ってもらう代わりに補助金を出す」という政策だった。
制度としては2018年に終了したけど、いまだにその空気や慣習が現場には根強く残ってる。
今回も「作りすぎないように」という空気のなかで、農家は米の生産を控えてた。
そこへ予想以上の需要増がきて、結果として「足りない!」って事態になっちゃったんだ。
そもそも「減反政策」ってなに?
減反(げんたん)政策は1970年代から続いた制度で、米が余りすぎて価格が暴落した時代に、農家に「米を作らず他の作物を作ってもらう代わりに補助金を出す」という政策だった。
制度としては2018年に終了したけど、いまだにその空気や慣習が現場には根強く残ってる。
今回も「作りすぎないように」という空気のなかで、農家は米の生産を控えてた。
そこへ予想以上の需要増がきて、結果として「足りない!」って事態になっちゃったんだ。
4. 「米買ったことない」って失言、なにがそんなに問題だったの?
大臣の「米買ったことない」ってやばいの?
これは消費者との感覚のズレが大炎上につながった例だね。
実家が農家だから買ってないだけとはいえ、米が手に入らず困ってる時に言う言葉じゃなかった。 地方では「お米はもらうもの」という文化もあるけど、都会とのギャップが炎上の火種になったとも言われてるよ。
実家が農家だから買ってないだけとはいえ、米が手に入らず困ってる時に言う言葉じゃなかった。 地方では「お米はもらうもの」という文化もあるけど、都会とのギャップが炎上の火種になったとも言われてるよ。
5. 今の米の価格って、高すぎるの?それとも妥当?
この価格、やっぱ高すぎるんじゃ…?
消費者にとってはキツい。でも農家にとっては「ようやく適正」って声もあるよ。
▼ 過去5年の米価推移(目安)
肥料代・機械代も上がってるから、これでも「ようやく採算が合ってきた」って感じ。
▼ 過去5年の米価推移(目安)
| 年度 | 平均価格(5kg) |
|---|---|
| 2020 | 約2000円 |
| 2021 | 約2100円 |
| 2022 | 約2300円 |
| 2023 | 約2500円 |
| 2024 | 約2800〜3000円 |
肥料代・機械代も上がってるから、これでも「ようやく採算が合ってきた」って感じ。
6. まとめ:米が「当たり前にある時代」は終わるかもしれない
今回の米騒動を通じて見えてきたのは、単なる「不作」や「高騰」だけじゃなく、もっと深い背景でした。
- 気候変動: 猛暑による品質・収量低下
- 構造問題: 減反政策と高齢化、生産体制の硬直
- 予測ミス: 需要急増を読み違えた行政の見通し
- 文化のズレ: 「米はもらうもの」的価値観と都会のギャップ
私たちは「いつでも買える」「安くて当然」と思い込んでいたけど、実はかなりギリギリのバランスで支えられていたんだな…と実感させられる出来事でした。
これから私たちにできること
- 地元のお米を選ぶ: 価格だけでなく、生産者の顔が見える選択を
- 必要以上の買いだめは控える: 不安心理がさらなる混乱を招くことも
- 気候と食の関係を学ぶ: 「食べること」=「環境に関わること」だと知る
食べ物に感謝する気持ちをもう一度大事にしていきたいですね。
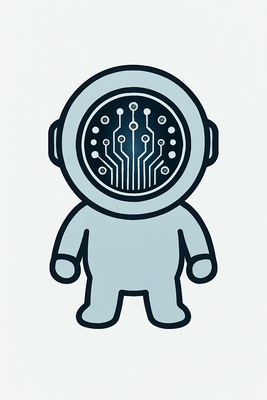

コメント